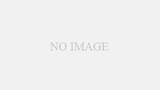スマートフォンやインターネットを使う高齢者が増える一方で、詐欺の被害も年々増加しています。特にシニア世代は、詐欺のターゲットになりやすいといわれています。
この記事では、インターネットに不慣れな方でもわかりやすいように、代表的なネット詐欺の手口とその対策方法を具体的に解説します。
1. フィッシング詐欺|本物そっくりなメールやSMS
「〇〇銀行からのお知らせ」や「荷物が届きませんでした」といった一見本物のようなメッセージが届き、記載されたリンクをタップすると、偽のログインページに誘導されます。そこで口座番号や暗証番号を入力してしまうと、情報が盗まれてしまうのです。
詐欺業者は、ロゴやレイアウトを本物そっくりに作ってくるため、見た目だけでは判断が難しいこともあります。
対策: メールやSMSのリンクはむやみに開かず、必ず公式アプリやブックマーク済みの正規サイトからログインするようにしましょう。
2. サポート詐欺|「ウイルスに感染しました」という警告画面
インターネットを見ていると突然「あなたのスマホはウイルスに感染しました」と大きな音と共に表示され、画面に表示された電話番号に電話するよう促されるケースです。これがいわゆる「サポート詐欺」です。
電話をかけると、相手はあたかも本物のサポートセンターのようにふるまい、不要なソフトの購入や高額な修理費用を請求してきます。
対策: 警告画面が表示されても慌てず、タブを閉じたり端末を再起動するだけで大半は解決します。正規のサポート窓口以外に電話をかけないことが鉄則です。
3. 偽ショッピングサイト詐欺
「セール中」「期間限定50%オフ」といった魅力的な広告に誘導されて開いたネットショップで商品を購入したものの、商品が届かない…という被害が後を絶ちません。中には実在する企業をかたるケースもあり、非常に巧妙です。
特に、SNS(InstagramやFacebookなど)の広告から誘導されるケースが増えています。
対策: 商品を購入する前に、販売者の会社情報・電話番号・レビュー・運営年数などを確認しましょう。「連絡先がない」「レビューが極端に良すぎる」などのサイトは要注意です。
注意点と詐欺を防ぐ習慣
- 知らない番号やメールには基本的に応じない
- 必ず一度「家族に相談する」習慣を
- ウイルス対策ソフトをインストールしておく
- 住所・口座番号・暗証番号はどんな理由でも教えない
よくある質問(Q&A)
Q. 知らない番号からの電話に出ても大丈夫?
A. 必要がある場合以外は出ないのが無難です。不在着信だけ残っていた場合も、折り返さないようにしましょう。
Q. メールで「当選しました」と書かれていたら?
A. 高額当選や賞金をうたう内容はほぼ詐欺です。リンクや添付ファイルは絶対に開かず、すぐに削除しましょう。
まとめ
ネット詐欺は年々巧妙になっていますが、ポイントを押さえておけば、被害を防ぐことは十分可能です。「少しでも不安に感じたら、まず誰かに相談する」ということを忘れないようにしましょう。
この記事は、「楽々ライフ編集部」が高齢者の安心・安全なインターネット利用をサポートするために執筆しました。